ネトゲガチャについて
ネトゲガチャについて/ネトゲガチャとは?
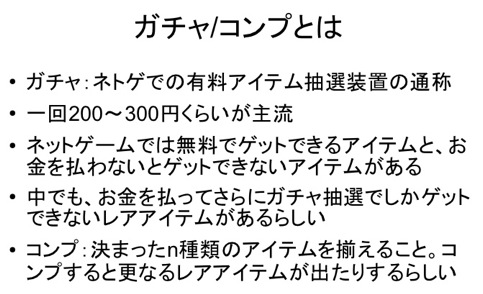
ランダムでアイテムを獲得できる課金システムの総称。欲しいアイテムが必ず手に入れられるわけではないので、熱くなりすぎないように自制しつつ利用するのが望ましい。
語源は、カプセルトイ(ガチャガチャ、ガシャポンなど)のように、お金(コイン)を入れてレバーを回すことで、カプセルに入った玩具・景品などを手に入れられる仕組みのものから来ている。
「ネトゲのガチャって批判されてるけど、ガチャやる為にネトゲやってるようなもんだろ?」
ネトゲのガチャにハマりすぎ定年男 妻から離婚を提案され取り乱し号泣 生活を犠牲にしてまでもどっぷりハマってしまうのが、いわゆるネトゲ(ネットワーク・ゲーム)。「ネトゲ廃人」という言葉もあるが、埼玉県に住む70才の女性Hさんは、定年した夫(63才)が、ネトゲにハマりすぎて困っているという。
もともと凝り性だった夫が、退職して、元の職場仲間とネットワーク・ゲームとやらを始めてから、会話が成り立たなくなっちゃった。 なにせ、朝6時に起きてスーツ着て出勤していた人が、今は午前中は爆睡。昼過ぎにむっくり起き出してきて、いつ着替えたんだかわからないフリースで、パソコンの前に這いだして行くのよ。
それで「お母さーん、お茶くれえー」とか、「昼もまだ食べてないぞー」ってコキ使うから頭にきて、「私、結婚記念日も、誕生日も、何ひとつプレゼントもらったことないよね~」ってイヤミを言ってやった。そしたら、何?
「ゲームの女戦士は、必ずお母さんの名前だし、ものすごく高価な装備だって付けてやってるんだぜ」って、こうよ。
あまりのことに呆れて「離婚しましょ」と言ったら、さすがに顔色変えて謝りまくって、「もう、ゲームはしません」と一筆書いて、ハンコもついた。
と、そのときよ。「オレはな、オレは…。わぁ~っ」ってワケのわからないこと言って、号泣。鼻水流して泣く63才の男が、私の夫かと思うと、こっちまで泣きたくなったわ。
夫に年金がついていなかったら、ま、今、いっしょにいないわね。
※ニュースポストより引用
↓↓↓
http://www.news-postseven.com/archives/20150122_299351.html
「ネトゲのガチャゲームは法的規制がない?」
ネトゲのガチャゲームについては何の法的規制もなく、
全てはゲーム運営企業の自由裁量、関連団体の自主規制になっています。
これは別に野放しになっていると云うわけではなく、
景品表示法や賭博禁止法をネットガチャゲームに当てはめても、
絵合わせを伴うコンプガチャ以外のガチャは、現行法では
違法性はまず存在せず、ようは 「モラル」 の問題になってしまう点が、
この問題をさらに複雑にしているからです。
ゲームのレアアイテムなどはゲームのファンにとっては喉から手が出るほど
欲しいもの、価値のあるものでしょうが、社会通念上、広く一般大衆に対して
強い射幸心を煽るほどの高額商品だとは云えないでしょう。
また自社製品を魅力的なものだと宣伝するのは虚偽に基づかなければ
違法ではありませんし、「欲しがる人間の勝手」 とも云えます。
現実的にはネトゲのアイテムなどはRMTで換金も可能ですし、
いわゆる 「相場」「時価」 のようなものも実体として存在します。
しかし原価からかけ離れたプレミアム価格をガチャ終了後に購入者がつけるのも、
それを別の第三者が買うのも合意があれば取り締まれませんし、
それを法的に取り締まったりすると、有体物としてのグッズや
フィギュアなどを含むプライズ系ゲーム全体がダメになってしまいます。
騙してでも売れてしまえば後の事はどうなろうと関係ない。
売れなくなれば他の客を探すだけ。
それでも売れなくなったら次は弱者に強引に売りつければよい。
焼畑農法ならぬ焼畑商法が最近非常に多い気がします。
義理を利用して強引に必要も無い保険を売ってみたり、
関係の無い特典を付けて購入をお願いしてみたり、
商品の持つ魅力とは関係の無い部分で売られている商品が多すぎます。
逆に言えば一度それらをやられてしまうと、
消費者が余程の馬鹿でない限りは当然次回は選択の対象から外れます。
「課金ガチャのスーパーレア出現率0%や確率操作はマジである。お前らはゲーム会社の手のひらで踊らされているだけだろ?」
オンラインゲームやモバイルゲーム、特にソーシャルゲームでおなじみの「ガチャ」はこれまでも幾度と無く議論の対象となってきた。
韓国のゲームサイトTHIS IS GAMEは、ガチャのような確率に影響されるカードやアイテムが登場するゲームの開発者やプランナーに匿名でインタビューを行った。その中で「ガチャ」を取り巻く開発側の事情が浮き彫りになってきた。

モバイルゲーム開発者Aさんの事例
Aさんは自社でサービスを行っているゲームのガチャの確率を見て驚愕した
ガチャで手に入る最高級アイテムが出る確率が0%に設定されていた
Aさんは企画者にこのことを尋ねると「ゲームバランスのためにわざわざ設定したのだから気にしなくていい」と言われた
ユーザーから疑われることを心配したAさんは強く抗議し、最終的に低確率で入手できるようになった
オンラインゲームプランナーBさんの事例
Bさんが勤めるオンラインゲーム開発会社で、オンラインゲームのイベントが企画されたイベントでポイントを集め、ポイントを使ってアイテムがランダムに入手できるというものランダムで手に入ることになっているアイテムの一つは確率が0%に設定されていた社内の会議では、「ゲーム内で流通する数量を制限するため」という理由で特に反論もなかった
「イベントでインフレが発生したらゲーム内経済を元に戻すのが難しくなるので、面倒なことにならないよう最初から出ないように」という考えだった
その後、イベント参加率を高めるためにサーバーで1個か2個は出てくるように調整されたBさんの会社で有料で販売されているガチャの最高級アイテムが出る確率は0.003%以下
モバイルゲーム事業者 Cさんの事例
モバイルゲームの企画と運営を担当しているCさん
Cさんは周囲の人たちに「もし私がユーザーなら、絶対にガチャにお金を使わない」と言っている
Cさんの会社のゲームのガチャでは、初心者以外は大して助けにもならないポーションや素材などが出る確率が90%以上確率をこのように設定するのは、ガチャをヘビーユーザー(廃課金者)のために作っているから
「こういったヘビーユーザーは、どういった確率でアイテムを引き当てられるかはよく知っている。しかし、ヘビーユーザーの課金がゲームを支えている状況で、ゲームに影響をあまり及ぼさずに売り上げを最大限引き上げる方法を考えると、様々な種類のアイテムをたくさん入れるほかない」とCさんは話す
開発者「確率操作?当然ある」
匿名を前提にあった開発者は、「全ての開発会社というわけではないが、いくつかの開発会社では確率操作をしている」と明かした。他の会社で行われていた事例はもちろん、自分たちが直接確率操作をした事例を挙げた開発者もいたようだ。
確率操作で主に活用されている方法は、特定のアイテムの出現確率を0%に制限したり、最大当選数を制限したり、価値が低いアイテム/カードが出てくる確率を大幅に高めるといったもの。
ガチャに関するガイドラインも会社ごとに異なっており、課金ガチャのアイテムの確率を内部的に決めておき、絶対に調整はしないという会社もあれば、「状況によって会議を行い決定する」という会社もある。
事実上これといったガイドラインがない「どんぶり勘定式」でガチャを販売しているところもあった。
小さなモバイルゲーム開発会社では、ガチャのような確率型アイテムをサービスした経験がある人が一人もいないという場合もあった。
Aさんは「計算すらせずにバランスに良くないという理由で確率を0%に調整したという話を聞いて驚いた。確率をある程度触ることができるとは予想していたが、ここまで無知な方法まであるとは思ってもみなかった」と答えた。
売り上げとゲームバランス
モバイルゲームはサービス開始後早い段階で約30万人のDAU(デイリーアクティブユーザー)を確保すれば安定したサービスが可能だという。
Bさんの会社のように最高級アイテムが出る確率が0.003%だった場合、30万人のユーザーがいればそのサーバーには既に約10個の最高級アイテムが解き放たれたものと同義である。
開発者は、「ゲームバランス」「経験不足」「ガチャアイテムを考慮していない設計」を確率操作をする理由に挙げた。開発者の立場では、バランスを考慮してガチャから出てくるものを設計しているべきだが、売上高のことを心配するとそれも簡単ではないというのが実情だ。
特定のアイテムが出てこないという疑惑を避けるために、一時的に確率を高める場合もある。取材に参加した開発者全員が、ユーザーのアイテム獲得状況を見てリアルタイムで確率を変えたことがあると認めたという。
こういった確率操作は当然ながらユーザーには全く知らされていない。ユーザーの立場では、同じお金を払ってガチャをする場合でも、「違う確率」が適用されることになる。多くのユーザーは自分が知らないうちに確率操作の影響を受けているわけだ。
単純な確率操作に留まらない場合も
確率操作が単純に確率操作だけで終わらない可能性があるという懸念もある。
とあるモバイルゲームの開発者は、「はっきりいって、出るかどうかもわからないアイテムでユーザーを騙すことができる状況で、他の問題が出てこないとは保証できない。売り上げに貢献するのなら、どんなことでもできるという意味だ。」と話す。
最低限の企業倫理すら守られていない状況で、他の問題が出てこない保証はない。
オンラインゲームの黎明期には、ゲーム運営者によるアイテムのコピーやRMT、能力値の操作などの問題が相次いで露呈した。モバイルゲームの開発会社の中にも確率操作だけではないいくつかの「疑惑」があるところもある。
「自主規制」をすれば企業倫理は守られるのか?との質問に開発者の回答は否定的で、強制力のない自主規制案では毎日毎日を生き延びるのが簡単ではないゲーム開発会社がこれを守る可能性は皆無だという。
業界全体が納得できる現実的なガイドラインと、これを守るための明確なビジョンの提示は絶対に必要だと開発者は口を揃えたとのこと。
韓国ではガチャのように運に左右される課金コンテンツにおいて、確率を公示することを義務付ける法案改正の動きがあるようだが、取材を行ったTHIS IS GAMEは、現在のような確率型のアイテム課金を中心としたモバイルゲームの収益モデルはゲーム産業の未来にとって危険因子である、と批判している。
日本においては、数年前にマスコミがソーシャルゲームのガチャの問題を取り上げてからは、以前ほど無分別な有料ガチャの仕組みは少なくなっている。
また、日本オンラインゲーム協会の運営ガイドラインでは次のように制定されている
4.有料ガチャの運用に関する事項
(1) ガチャアイテムの提供割合は、事前の告知無くこれを変更しない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでは無いが、変更の可能性が生じた時点から可及的速やかにその旨を告知すよう努めるものとする。
(2) 有料ガチャの運用については、運用責任者を定めることとする。
□ a.運用責任者は、有料ガチャの提供の前に、当該有料ガチャにおけるガチャアイテムの提供割合を承認するものとし、当該承認の事実を書面等により記録する仕組みを社内に構築するものとする。
□ b. 運用責任者は、有料ガチャが設定された通り適切に稼働することを確認し、書面等により確認の結果等を記録する仕組みを社内に構築するものとする。
(3) 有料ガチャにおけるガチャアイテムの提供割合を安易に変更出来ないよう、システムの設計に留意するものとする。
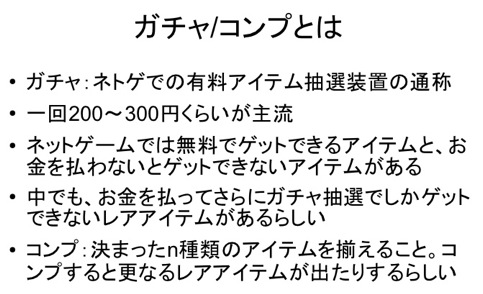
ランダムでアイテムを獲得できる課金システムの総称。欲しいアイテムが必ず手に入れられるわけではないので、熱くなりすぎないように自制しつつ利用するのが望ましい。
語源は、カプセルトイ(ガチャガチャ、ガシャポンなど)のように、お金(コイン)を入れてレバーを回すことで、カプセルに入った玩具・景品などを手に入れられる仕組みのものから来ている。
「ネトゲのガチャって批判されてるけど、ガチャやる為にネトゲやってるようなもんだろ?」
ネトゲのガチャにハマりすぎ定年男 妻から離婚を提案され取り乱し号泣 生活を犠牲にしてまでもどっぷりハマってしまうのが、いわゆるネトゲ(ネットワーク・ゲーム)。「ネトゲ廃人」という言葉もあるが、埼玉県に住む70才の女性Hさんは、定年した夫(63才)が、ネトゲにハマりすぎて困っているという。
もともと凝り性だった夫が、退職して、元の職場仲間とネットワーク・ゲームとやらを始めてから、会話が成り立たなくなっちゃった。 なにせ、朝6時に起きてスーツ着て出勤していた人が、今は午前中は爆睡。昼過ぎにむっくり起き出してきて、いつ着替えたんだかわからないフリースで、パソコンの前に這いだして行くのよ。
それで「お母さーん、お茶くれえー」とか、「昼もまだ食べてないぞー」ってコキ使うから頭にきて、「私、結婚記念日も、誕生日も、何ひとつプレゼントもらったことないよね~」ってイヤミを言ってやった。そしたら、何?
「ゲームの女戦士は、必ずお母さんの名前だし、ものすごく高価な装備だって付けてやってるんだぜ」って、こうよ。
あまりのことに呆れて「離婚しましょ」と言ったら、さすがに顔色変えて謝りまくって、「もう、ゲームはしません」と一筆書いて、ハンコもついた。
と、そのときよ。「オレはな、オレは…。わぁ~っ」ってワケのわからないこと言って、号泣。鼻水流して泣く63才の男が、私の夫かと思うと、こっちまで泣きたくなったわ。
夫に年金がついていなかったら、ま、今、いっしょにいないわね。
※ニュースポストより引用
↓↓↓
http://www.news-postseven.com/archives/20150122_299351.html
「ネトゲのガチャゲームは法的規制がない?」
ネトゲのガチャゲームについては何の法的規制もなく、
全てはゲーム運営企業の自由裁量、関連団体の自主規制になっています。
これは別に野放しになっていると云うわけではなく、
景品表示法や賭博禁止法をネットガチャゲームに当てはめても、
絵合わせを伴うコンプガチャ以外のガチャは、現行法では
違法性はまず存在せず、ようは 「モラル」 の問題になってしまう点が、
この問題をさらに複雑にしているからです。
ゲームのレアアイテムなどはゲームのファンにとっては喉から手が出るほど
欲しいもの、価値のあるものでしょうが、社会通念上、広く一般大衆に対して
強い射幸心を煽るほどの高額商品だとは云えないでしょう。
また自社製品を魅力的なものだと宣伝するのは虚偽に基づかなければ
違法ではありませんし、「欲しがる人間の勝手」 とも云えます。
現実的にはネトゲのアイテムなどはRMTで換金も可能ですし、
いわゆる 「相場」「時価」 のようなものも実体として存在します。
しかし原価からかけ離れたプレミアム価格をガチャ終了後に購入者がつけるのも、
それを別の第三者が買うのも合意があれば取り締まれませんし、
それを法的に取り締まったりすると、有体物としてのグッズや
フィギュアなどを含むプライズ系ゲーム全体がダメになってしまいます。
騙してでも売れてしまえば後の事はどうなろうと関係ない。
売れなくなれば他の客を探すだけ。
それでも売れなくなったら次は弱者に強引に売りつければよい。
焼畑農法ならぬ焼畑商法が最近非常に多い気がします。
義理を利用して強引に必要も無い保険を売ってみたり、
関係の無い特典を付けて購入をお願いしてみたり、
商品の持つ魅力とは関係の無い部分で売られている商品が多すぎます。
逆に言えば一度それらをやられてしまうと、
消費者が余程の馬鹿でない限りは当然次回は選択の対象から外れます。
「課金ガチャのスーパーレア出現率0%や確率操作はマジである。お前らはゲーム会社の手のひらで踊らされているだけだろ?」
オンラインゲームやモバイルゲーム、特にソーシャルゲームでおなじみの「ガチャ」はこれまでも幾度と無く議論の対象となってきた。
韓国のゲームサイトTHIS IS GAMEは、ガチャのような確率に影響されるカードやアイテムが登場するゲームの開発者やプランナーに匿名でインタビューを行った。その中で「ガチャ」を取り巻く開発側の事情が浮き彫りになってきた。

モバイルゲーム開発者Aさんの事例
Aさんは自社でサービスを行っているゲームのガチャの確率を見て驚愕した
ガチャで手に入る最高級アイテムが出る確率が0%に設定されていた
Aさんは企画者にこのことを尋ねると「ゲームバランスのためにわざわざ設定したのだから気にしなくていい」と言われた
ユーザーから疑われることを心配したAさんは強く抗議し、最終的に低確率で入手できるようになった
オンラインゲームプランナーBさんの事例
Bさんが勤めるオンラインゲーム開発会社で、オンラインゲームのイベントが企画されたイベントでポイントを集め、ポイントを使ってアイテムがランダムに入手できるというものランダムで手に入ることになっているアイテムの一つは確率が0%に設定されていた社内の会議では、「ゲーム内で流通する数量を制限するため」という理由で特に反論もなかった
「イベントでインフレが発生したらゲーム内経済を元に戻すのが難しくなるので、面倒なことにならないよう最初から出ないように」という考えだった
その後、イベント参加率を高めるためにサーバーで1個か2個は出てくるように調整されたBさんの会社で有料で販売されているガチャの最高級アイテムが出る確率は0.003%以下
モバイルゲーム事業者 Cさんの事例
モバイルゲームの企画と運営を担当しているCさん
Cさんは周囲の人たちに「もし私がユーザーなら、絶対にガチャにお金を使わない」と言っている
Cさんの会社のゲームのガチャでは、初心者以外は大して助けにもならないポーションや素材などが出る確率が90%以上確率をこのように設定するのは、ガチャをヘビーユーザー(廃課金者)のために作っているから
「こういったヘビーユーザーは、どういった確率でアイテムを引き当てられるかはよく知っている。しかし、ヘビーユーザーの課金がゲームを支えている状況で、ゲームに影響をあまり及ぼさずに売り上げを最大限引き上げる方法を考えると、様々な種類のアイテムをたくさん入れるほかない」とCさんは話す
開発者「確率操作?当然ある」
匿名を前提にあった開発者は、「全ての開発会社というわけではないが、いくつかの開発会社では確率操作をしている」と明かした。他の会社で行われていた事例はもちろん、自分たちが直接確率操作をした事例を挙げた開発者もいたようだ。
確率操作で主に活用されている方法は、特定のアイテムの出現確率を0%に制限したり、最大当選数を制限したり、価値が低いアイテム/カードが出てくる確率を大幅に高めるといったもの。
ガチャに関するガイドラインも会社ごとに異なっており、課金ガチャのアイテムの確率を内部的に決めておき、絶対に調整はしないという会社もあれば、「状況によって会議を行い決定する」という会社もある。
事実上これといったガイドラインがない「どんぶり勘定式」でガチャを販売しているところもあった。
小さなモバイルゲーム開発会社では、ガチャのような確率型アイテムをサービスした経験がある人が一人もいないという場合もあった。
Aさんは「計算すらせずにバランスに良くないという理由で確率を0%に調整したという話を聞いて驚いた。確率をある程度触ることができるとは予想していたが、ここまで無知な方法まであるとは思ってもみなかった」と答えた。
売り上げとゲームバランス
モバイルゲームはサービス開始後早い段階で約30万人のDAU(デイリーアクティブユーザー)を確保すれば安定したサービスが可能だという。
Bさんの会社のように最高級アイテムが出る確率が0.003%だった場合、30万人のユーザーがいればそのサーバーには既に約10個の最高級アイテムが解き放たれたものと同義である。
開発者は、「ゲームバランス」「経験不足」「ガチャアイテムを考慮していない設計」を確率操作をする理由に挙げた。開発者の立場では、バランスを考慮してガチャから出てくるものを設計しているべきだが、売上高のことを心配するとそれも簡単ではないというのが実情だ。
特定のアイテムが出てこないという疑惑を避けるために、一時的に確率を高める場合もある。取材に参加した開発者全員が、ユーザーのアイテム獲得状況を見てリアルタイムで確率を変えたことがあると認めたという。
こういった確率操作は当然ながらユーザーには全く知らされていない。ユーザーの立場では、同じお金を払ってガチャをする場合でも、「違う確率」が適用されることになる。多くのユーザーは自分が知らないうちに確率操作の影響を受けているわけだ。
単純な確率操作に留まらない場合も
確率操作が単純に確率操作だけで終わらない可能性があるという懸念もある。
とあるモバイルゲームの開発者は、「はっきりいって、出るかどうかもわからないアイテムでユーザーを騙すことができる状況で、他の問題が出てこないとは保証できない。売り上げに貢献するのなら、どんなことでもできるという意味だ。」と話す。
最低限の企業倫理すら守られていない状況で、他の問題が出てこない保証はない。
オンラインゲームの黎明期には、ゲーム運営者によるアイテムのコピーやRMT、能力値の操作などの問題が相次いで露呈した。モバイルゲームの開発会社の中にも確率操作だけではないいくつかの「疑惑」があるところもある。
「自主規制」をすれば企業倫理は守られるのか?との質問に開発者の回答は否定的で、強制力のない自主規制案では毎日毎日を生き延びるのが簡単ではないゲーム開発会社がこれを守る可能性は皆無だという。
業界全体が納得できる現実的なガイドラインと、これを守るための明確なビジョンの提示は絶対に必要だと開発者は口を揃えたとのこと。
韓国ではガチャのように運に左右される課金コンテンツにおいて、確率を公示することを義務付ける法案改正の動きがあるようだが、取材を行ったTHIS IS GAMEは、現在のような確率型のアイテム課金を中心としたモバイルゲームの収益モデルはゲーム産業の未来にとって危険因子である、と批判している。
日本においては、数年前にマスコミがソーシャルゲームのガチャの問題を取り上げてからは、以前ほど無分別な有料ガチャの仕組みは少なくなっている。
また、日本オンラインゲーム協会の運営ガイドラインでは次のように制定されている
4.有料ガチャの運用に関する事項
(1) ガチャアイテムの提供割合は、事前の告知無くこれを変更しない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでは無いが、変更の可能性が生じた時点から可及的速やかにその旨を告知すよう努めるものとする。
(2) 有料ガチャの運用については、運用責任者を定めることとする。
□ a.運用責任者は、有料ガチャの提供の前に、当該有料ガチャにおけるガチャアイテムの提供割合を承認するものとし、当該承認の事実を書面等により記録する仕組みを社内に構築するものとする。
□ b. 運用責任者は、有料ガチャが設定された通り適切に稼働することを確認し、書面等により確認の結果等を記録する仕組みを社内に構築するものとする。
(3) 有料ガチャにおけるガチャアイテムの提供割合を安易に変更出来ないよう、システムの設計に留意するものとする。
